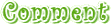保有資格:社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員。ついでに日商簿記2級・全商簿記1級
(Twitter@renrinoeda2)
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
引きこもりの年末年始
今年も今日で終わりです。
私は29日から3日までが正月休みとなっていますが、昨年からの父のことの対応で、事務仕事がかなり滞っているので、正月休みは、自宅で仕事です。
しかし、事実上の過労で体調がかなり悪いので、どこまで仕事の追い上げが出来るかわかりません。
昨日も、一昨日も、休み休みやっていたので、それほど仕事は、はかどっていません。
今日も午前中は気分が悪くなり、横になっていました。
まだ、無理をすると、本当に倒れてしまうので、その加減が難しいです。
9月頃から身体の不調が顕著に出てきました。
最初は、胸が苦しくなってくることが多くなりました。
これは、若い頃からの、『オーバ-ワークだぞ!』という身体からのサインなので、そういうときは、必ず仕事のペースを落とすようにしてきました。
しかし、今回は昨年の11月から父のことで動き回っていたので、いつものペースの落とし方では、体調は戻りませんでした。
体調が悪ければ、判断力が落ちます。
判断力が落ちた結果、仕事のミスを連発して、社長に迷惑をかける結果になりました。
社長も私の事情を考慮して下さり、大目に見て下さいましたが、ミスはミスです。
このままではまずいな・・・と、思い始めました。
しかし、10月の中頃から別の症状が出始めました。
朝、起きて、1時間くらいたつと、頭がくらくらして動けなくなるようになりました。
動けない時間はあっという間に長くなっていき、大体2時間は、まともに動けなくなりました。
こういうときは、椅子に座ってじっとしているか、辛すぎるときはベッドに横になり、収まるのを待つしかありませんでした。
仕事に遅れないようにするためには、動けない時間も計算して、早く起きるしかありませんでした。
それでも、疲れすぎて起きられないときもあったし、動けない時間が4時間も続いて、結果的に遅刻をすることが何度もありました。
もしかして、この症状は頸椎ヘルニアの影響かも、と思い、いつもの整形外科に受診しました。
先生は、原因は頸椎ヘルニアからでもなく、三半規管からでもないとのこと。
『働き過ぎで、疲れすぎだよ、無理しすぎだよ。本当は少し仕事を休めるといいんだけどね~。』
『頭がくらくらするのは、酷い疲労で身体の筋肉が固まりすぎて、血の巡りが悪くなって、起きているんだ。高齢者によくある『起立性低血圧』のような状態になってるんだよ。』
とのこと。
つまり、遠回しで『過労』と言われたような感じでした。
先生が『仕事を休め』と言わないのは、私の仕事がケアマネである事を知っているから、安易は休めないことを知っているからです。
頸椎ヘルニア発症時に全身の激痛で数ヶ月苦しんだときも、私は仕事を休まなかったので、先生も私に『仕事を休め』と言っても無駄だと思ったのでしょう。
でも、先生の診断を受けて、自分の身体不良の原因が軽視できない状態である事が解りました。
ですから、社長と相談し、今後は『仕事の追い上げ』が終わり『体調が戻る』までは、『担当件数を減らす』ことにしました。
介護30件、予防3件。(今までは、介護35件、予防3件でした)
当面は、この件数で行くので、給与が3万下がります。
生活が苦しくなりますが、職場にかなりの迷惑をかけたので、仕方がありません。
しかし、両親は、私のこの状況を理解する気はないようです。
先ほども、母から『初詣』のことで電話がありました。
毎年、一緒に行っていたので、母はそのつもりでいたのでしょう。
私は、今は実家の家族と距離を置きたいし、それよりも体調が悪いので、初詣どころではありません。仕事の追い上げもしなくてはなりません。
実家には、『体調がとても悪いし、その上で仕事の追い上げをしないといけないから、静養している時間もない、だから、正月休みは自宅で仕事をするので、帰らない』と、言ってあります。
それでも、母は、私の体調より、お札を帰しに行くことばかりを気にしてました。
当然私は『まだ具合が悪いし、その上で休みの間も自宅で仕事しないといけないから、どこにも行ける状態じゃない』と伝えました。
しかし、母から私の体調を気にする言葉は、一切出てきませんでした。
何のために、一年間自分のことを犠牲にして、父のことで奔走してきたのか・・・正直解らなくなりました。
だから、今は、家族と距離を置きたいのです。会いたくないのです。
『今度の正月は父の最後の正月になるかもしれない。』
昨年の今頃も、同じことを思っていました。
今の父は、体力は落ちてきたけれど、癌の進行は今のところ遅く、日常生活に大きな支障は出ていないようです。
ただ、『3度の飯より好きな釣り』に行っていないようなので、それが父の今の体調を全て物語っています。
だから、本当は、娘として正月は実家へ行くべきなのは解っています。
でも、今、両親と会っても、私には、両親とまともな会話は出来ません。
ケンカになるかもしれないし、そうならなくても、普通の会話が出来なければ、後味の悪い正月になってしまうだけです。
それでは、私が正月に実家に行く意味がありません。
そして、間違いなく、私が不愉快な思いをして、気分が悪くなって帰ってきて、精神安定剤を飲んで寝込むだけです。
だから、正月はひとりで過ごすことにしました。
自宅に引きこもって、休み休みしながら、体調を相談しながら、仕事の追い上げをします。
こんな一年間でしたので、ケアマネとしての勉強が、今年は全く出来ませんでした。
もうすぐ、ケアマネになって2年半になります。
そろそろ、『今の自分の『引き出し』の数だけでは、ケアマネ業務を行なっていくことに限界が来ているな』、と思ってます。
『ケアマネとして、もっと知識と視野を広げたい』。
そう思うようになりました。
ですから、来年は『きちんと勉強しよう』と、思っています。
3月までに仕事の追い上げをして(←私を見かねた社長が、1ヶ月期限を延ばしてくれました)、来年度から、勉強が出来る状態にしたいと思ってます。
実家、特に父とのことは、これからどう関わっていくか、まだ私のなかで結論が出ていません。
選択肢のなかに、『縁を切る』ことも、正直あります。
親子の縁を切るなど、そう簡単にできることではありませんが、長い年月の間の色々なことが積み重なり、その結果私のなかで、家族との関係に限界が来ていることも事実です。
叔母には、『お前は充分に親孝行したから、もう、実家のことは考えるな。お前がしてくれたこと何も解っていない両親にこれ以上してやることはない。これからは、自分自身のことを大事にしなさい』と言われました。
自分自身の身の処し方を決められない人間が、ケアマネとしてご利用者様とそのご家族の支援が出来るのかと、自問自答をすることもあります。
そんな未熟者ではありますが、それでもこれからも、ケアマネとしての仕事に真摯に取り組みたいと思います。
この一年、自分が『キーパーソン』をやって、身にしみたことがあります。
『キーパーソン』は、『自分のことを後まわしにしないと、出来ないこと』なのだと、痛感しました。
ケアマネになったばかりの頃、ご利用者様のご家族が、自分の健康を損ねながら、介護をしている姿を目にしたとき、どうして、ご家族が自分の病院へ行かないのか、あのときの私には、わからなかった。
でも、自分が頸椎ヘルニアの激痛に耐えなから、父のことを優先して動き、自分の病院受診を後まわしにして、土曜日に振り替え出勤を、4ヶ月間の間ほぼ毎週していたときに、思いました。
『ああ、介護をしている家族、特にキーパーソンの方は、こうやって身体を壊していくのだ』
そして
『介護と仕事の両立は、とても難しいことなのだ』と。
私は『介護』はまだしていませんが、そのことを、『当事者として経験した』ときに、専門職では解らない、『当事者でしか解らない心情というものがある』ことを知りました。
しょせん、専門職が知っていることは『知識』でしかなく、『実体験』ではありません。
そのことを踏まえて、ご利用者様とご家族と向き合わないと、知らないうちにご利用者様とご家族を傷つけてしまうでしょう。
安易に『貴方の辛いお気持ち解ります』とは、やはり言ってはいけないのです。
相手のことを完全に理解することは、人間にはとうてい出来ないことです。
『自分は、クライアントの気持ちをしっかりと理解している』と言い切れる専門職は、私から見れば、単なる傲慢でしかありません。
『相手を完全に理解することは、人間には出来ないこと』
でも、それを踏まえた上で、『少しでも』ご利用者様とご家族の心情を理解していく努力を続けていくことこそが、専門職として大切なことだと、私は考えています。
そして、もうひとつ。
『謙虚な姿勢で、ご利用者様とご家族と向き合っていく。』
『でも、必要なときは、あえて自分の言動に責任をもち、覚悟を決めて行動を起こす。』
義務と責任ばかりは多いけれど、権限はひとつもないという、ケアマネージャーの立場で、出来ることには限界がある事は、仕方がないことでもあります。
でも、ご利用者様とご家族の人生と生活を守るために、その限界を越えて、行動をする覚悟も必要なときがあることを知りました。
それを、先日彼岸へ旅だったAさんとの最後の1ヶ月間の支援から学ばせていただきました。
『それは私の立場では出来ない』と、支援者がみな、踏み出さないでいたら、打破できないことが沢山ある。
現状の打破の為に、あえて、己の立場の限界から一歩ふみだすことを、支援者の誰かがしないといけないこともある。
そのときに、ご利用者様とご家族を守るために、その行動が出来る専門職になりたいと、私は今、思っています。
教科書通りには、支援は出来ません。
きれい事でも支援は出来ません。
『ご利用者様とご家族』そのケースごとに合わせて、ご支援をしていかなくてはけません。
バイステックのケースワークの7原則の『個別性の原則』であります。
最近、バイステックの7原則の大切さを感じることがあります。
『教科書嫌い』の私にとっては、これは考えられなかった視点です。
これも『専門職としての基礎』となる考え方にもつながるのかもしれません。
それでも、これからも私は、泥臭いままで、『ご利用者様とご家族の人生と生活を守る』ことが出来るケアマネを目指して精進していきたいと思います。
今年は、あまり更新できませんでしたが、毒吐きブログに来て下さり、本当にありがとうございました。
来年も、毒吐きを続けたいと思いますので、気が向いたら、覗きに来てやって下さい。
どうか、皆様も良いお年を、お迎え下さいますように。
かたつむり
なかなか、コメントのお礼のお返事を書くことができなくて、申し訳ありません。
どうか、ご了承くださいますようお願いいたします。
(本当に、本当に、ずっと書けずにごめんなさいっ)
ランキングに参加しています
ぜひ、ぽちっと押してやってください。
にほんブログ村<!--
にほんブログ村
twitter(←オタクサイトと共通です、ご注意を)

 管理画面
管理画面